公文書管理、法制化へ一歩踏み出す
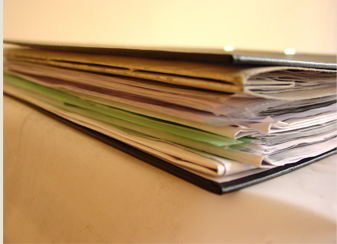
公文書の保存については、2001年の「申し合わせ」により、一定の保存期限後(最長30年)、資料的価値の高いものを国立公文書館 に移管すると定められましたが、移管には省庁側の「合意」を要すため、今年3月末で内部保存期間が満了した行政文書(公文書)約104万件のうち、国立公文書館に移管されたのは僅か0.7%という有様でした。
に移管すると定められましたが、移管には省庁側の「合意」を要すため、今年3月末で内部保存期間が満了した行政文書(公文書)約104万件のうち、国立公文書館に移管されたのは僅か0.7%という有様でした。
いっぽう、自衛隊の艦船が部内規定を無視して航海記録を処分していたり、厚生労働省で薬害のリストが放置されていたり、社会保険庁で年金の記録が散逸して いたりという問題が次々に露見し、福田首相は今年2月、公文書担当大臣を新設(上川陽子氏が初代担当相、さきの内閣改造で中山恭子氏に引き継がれる)し、 その下で「公文書管理の在り方等に関する有識者会議 」(尾崎護座長)を繰り返し開催して、この問題について検討してきました。
」(尾崎護座長)を繰り返し開催して、この問題について検討してきました。
去る7月1日、有識者会議は中間報告をとりまとめ上川大臣に提出しました。中間報告の第一の柱は、公文書管理の在り方を抜本的に見なおし、文書の作成、利用、保管についての統一的基準を定める「公文書管理法」(仮称)を制定することです。第二の柱は、内閣府に公文書管理の「司令塔」となる担当機関を設置 し、現在独立行政法人である国立公文書館を同機関に統合するか「特別の法人」に改組するというものです。人員も現状の50人程度から「数百人規模」にまで 増やすとしています。アメリカの国立公文書館の職員数は2,500人、英国180人、韓国120人と比べてみても、日本の現状が不十分なのは明らかです。 有識者会議は、「公文書管理法」(仮称)の内容などについて、今後討議し、10月に最終報告を提出予定で、来年の通常国会での法案成立をめざしています。
法律が施行されると、官公庁だけでなく、公共事業を請け負う企業にも、同じレベルの文書管理が求められることになると思われます。民間においても、内部統制や企業コンプライアンスの関係から文書管理強化の動きが目に見えて強まっています。

ヘリテージサービス事業部アーカイブ担当 中川 洋
歴史系博物館学芸員として資料の収集・管理や展示・教育業務に携わり、現職に就く。
現在は、企業および学園アーカイブのコンサルティング、プランニング、マネジメントに従事。


